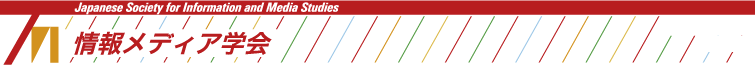
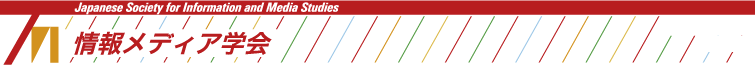
第23回研究大会が開催されました
■ 大会報告
2024年6月22日(土)に、情報メディア学会第23回研究大会をハイブリッド開催いたしました。会場は跡見学園女子大学文京キャンパス(東京都文京区大塚1-5-2)のおよびオンラインによるハブリッド開催となりました。ただし、ポスター発表およびポスターディスカッションは現地のみの開催としました。
司会は杉本ゆか氏(明星大学)により行われ、参加者は現地:48名(会員27、非会員9、学生非会員6、賛助会員6)、オンライン(申込):69名(会員11、非会員51、学生非会員7)が参加いたしました。
■ 開会
角田裕之会長より開会挨拶をいただきました。
■ 基調講演
木村麻衣子氏(日本女子大学)より「AIで作れるでしょと言われてしまう日本の図書館目録について」と題した基調講演を行なっていただきました。
木村氏は、目録作成作業は従来から合理化の対象であったことを述べられたのち目録を3つの側面(知識体系の表現、コレクションリスト、ディスカバリー・ツール)に整理した論を述べられました。
つづいて日本の図書館目録の現状、すなわち、検索・典拠コントロール・人材等の問題に触れ、これらの解決方法としての生成AIにおける難しさについてご自身の考えを述べられました。
最後に、今後の目録超高度化時代の到来について、多くの作業はAI化されるとともに、少数のより高度に訓練された職員が業務に携わるようになるだろうと語られました。
■ シンポジウム
今野創祐氏(東京学芸大学)にコーディネーターを務めていただき、「目録の現状と課題:意義を再確認する」と題するシンポジウムを開催しました。
パネリストとして基調講演講師の木村氏および渡邊隆弘氏(帝塚山学院大学)、橋詰秋子氏(実践女子大学)をお迎えしました。最初に今野氏よりパネリストの紹介をいただき、以下の登壇者2名による講演が行われました。
■ 渡邊隆弘氏講演
渡邉氏は件名標目表、特に国立国会図書館件名標目標や基本件名標目標について関係性や利用に関しての所見を述べられました。付与におけるポリシー、構造、コントロールからOPAC等の検索サービスにおける関係まで、幅広い観点で論ぜられ、ご本人が望ましいであろうと思う件名について述べられました。また、歴史的な背景を近年のLOD化までを含め紹介頂きました。
■ 橋詰秋子氏講演
橋詰氏は組織法の観点からの著作について、特に書誌レコードの観点から意見を述べられました。カタロガーが著作を捉える時、FRBRやその後継の概念による精緻化された著作モデルでは著作は連続的と捉えられるが、レコードはこのアクセスポイントとして位置付けられるというお考えを紹介され、このような行為はアートに近いと評されました。
また、日本における問題としてカタロガーの人材問題を取り上げられ、AIによる業務のサポートにも触れられました。
■ ディスカッション
ディスカッションでは4名の登壇者の方だけでなく会場の参加者の方も交え、生成AIの利用、人材育成、関連する海外の状況などについて活発な討議が行われました。
■ 総会
現地およびオンライン参加の会員にて総会が行われました。
■ ポスター発表
ポスター発表では以下の発表が行われました。(◎は代表者)
ポスター発表優秀賞では「小規模自治体の学校図書館における図書の量的整備状況と課題」(代表:原田久之氏)と、「復刻の人 ー野田宇太郎と日本郷土文藝叢書刊行会ー」(岡野裕行氏)の2件が同率で受賞しました。
■ 賛助会員ライトニングトーク
賛助会員ライトニングトークとして日本事務機器株式会社より製品のご案内を頂きました。
■ ブース出展
以下の団体よりブース出展が行われました。
株式会社樹村房 日外アソシエーツ株式会社 日本事務機器株式会社
■ 表彰式・閉会
ポスター発表優秀賞の表彰式がおこなわれました。今回のポスター発表優秀賞は同率で2件となりました。最後に、長塚隆副会長より閉会挨拶をいただき、閉会となりました。
■ プログラム概要
| 10:00 | 開場 (会場:跡見学園女子大学 文京キャンパス) |
| 10:15 | Zoom開場 |
| 10:30 | 開会挨拶 |
| 10:35 |
基調講演 |
| 11:35 | 休憩 |
| 11:35-12:35 | 総会 |
| 13:00 |
シンポジウム |
| 14:40 | 休憩 |
| 15:00 | ポスターライトニングトーク・賛助会員ライトニングトーク |
| 15:40 | ポスターディスカッション |
| 16:20 | 表彰式,閉会挨拶 |
■ 第23回研究大会企画委員会
委員長 今野 創祐 東京学芸大学
委 員 天野 晃 国立情報学研究所
委 員 佐藤 翔 同志社大学
委 員 下山佳那子 八洲学園大学
委 員 新藤 透 國學院大學
委 員 杉本 ゆか 明星大学
委 員 千 錫烈 関東学院大学
委 員 西田 洋平 東海大学
委 長 日向 良和 都留文科大学
委 員 長谷川幸代 跡見学園女子大学
小規模自治体の学校図書館における図書の量的整備状況と課題
原田久之(八洲学園大学),野口久美子(八洲学園大学)
1. 最優秀ポスター発表受賞おめでとうございます。受賞について一言お願いいたします。
原田氏:賞をいただき、ありがとうございます。この領域へのこういったアプローチに 対して評価をいただき、うれしく思います。今後、この分野での研究が進むこ とのきっかけになればと考えます。
2. どういった経緯で今回の研究を行うことになったのでしょうか?
原田氏:ライトニングトークにて研究背景として申しましたように、少子化により小規 模校が増えています。小規模校のメリットをいかし、デメリットを緩和して、 教育の充実を図るには、学校図書館の活用が重要となります。しかし、小規模 校での活用研究は少ないのが現状です。そこで、この研究では、まず、「図書の 量的整備」といった基本的な状況に注目しました。
野口氏:原田さんは2019年秋に本学に編入学し、図書館情報学や博物館学を中心に学 修を進めていらっしゃいます。今回の研究を行う直接のきっかけとなったのは、 「特別研究(学校図書館学)」の履修です。本学の学校図書館専門職養成応用 プログラムの選択科目であり、学校図書館研究を行うために必要な基礎的な素 養を身につけることを目的としています。本科目では研究成果を広く世の中に 発信することも推奨しており、学校図書館関係者のみならず、多様な分野の研 究者・実践者が集う情報メディア学会での発表が望ましいと考え、原田さんに お勧めした次第です。
3. ポスター発表の研究の概要について教えてください。
原田氏:この研究では、小規模な小学校の学校図書館での、量的整備状況と図書予算の 関係について数量的に分析しました。公開されている既存調査のデータ、おも に、文部科学省による現状調査と全国学校図書館協議会等による施策実施調査 のデータを再集計しています。結果として、学校規模が小さいことは量的整備 を進められない共通要因ではないこと、整備状況の経年変化には停滞あるいは 低下がおきる場合があることがわかりました。さらに、目標冊数を達成し維持 していても、図書予算額には格差状態の固定化が見られることが明らかになり ました。
4. デザイン面などで工夫した点を教えてください。
原田氏:基本的には、予稿の章立て、1.背景と目的、2.方法、3.結果、4.考察を枠に囲み、 メインのフローとして、順にA0サイズに配置しました。そのうえで、ポスター 上の目線の流れを補助する工夫として、サブフローの矢印を加えてあります。サ ブフローは、まず、1.背景で、全国の小学校の全体状況を「森」として俯瞰しま す。次に、3.結果で、分析によるドリルダウンにより、個々の学校の状況を「木」 として把握します。そして、1.背景の全体状況に戻ると、違った森が見えてくる という流れです。
5. ポスター制作にあたっての苦労話やエピソードなどありましたら、教えてください。
原田氏:一般のプレゼンソフトで原稿を作成し、外部にポスター印刷を依頼する場合に は留意すべき点があります。まず、PC画面での彩度の高い色は、印刷では彩度 が再現できないので使わないことです。次に、文字や線・面の装飾(グラデーショ ン、影やぼかし)は、印刷では表現されず意図しない結果となることが多いので 使わないことです。最後に、印刷物の受領の日程には余裕をみてください。宅配 業者の事情により予定の翌日になるというハプニングがありました。
6. ポスター発表時の会場の人からの反応はいかがでしたでしょうか?
原田氏:いろいろな視点からの、示唆に富む質問や意見をいただき、ありがとうござい ました。例えば、「整備状況をより具体的に評価するときには、実際の利用者で ある児童や教員による評価と、そこを職場とする学校司書や司書教諭による評価 も重要」、との指摘がありました。実際、会場の参加者には学校司書の方もおら れ、同規模自治体の小学校での予算の違いについての実感を伺うことができまし た。また、慣れないポスター発表でしたので、「各々の分析結果についてはわか るが、ポスターとしては何がいいたいのかがわかりにくい。今後の研究・発表で は、今回の予備的な知見をもとに絞り込むとよい」、といった意見もいただきま した。
7. ポスター発表の論文発表のご予定は?
原田氏:この発表をもとにまとめることができましたら、貴学会誌「情報メディア研究」
への投稿ができればと思います。それにより、学校図書館研究者による議論が深ま
り、学校図書館を支援・指導する関係者の取組みが進化し、ひいては、学校図書館
の現場の方々のさまざまな業務の改善につながればと考えております。
復刻の人 ―野田宇太郎と日本郷土文藝叢書刊行会―
岡野裕行(皇學館大学)
1. 最優秀ポスター発表受賞おめでとうございます。受賞について一言お願いいたします。
ありがとうございます.情報メディア学会でのポスター発表はこれまでに何度か行っているのですが,この賞をいただくのは今回が初めてのことなのでとても嬉しいです.
2. どういった経緯で今回の研究を行うことになったのでしょうか? 経緯を教えてください。
私はここ最近,文学散歩とその考案者である野田宇太郎について研究をしています.数年前から野田宇太郎が関与した出版物を「日本の古本屋」などを活用して買い集めていたのですが,その調査の過程でいくつかの復刻出版物を手がけていたことを知りました.最初に入手したのは夏目漱石著『吾輩は猫である』の明治村版です.野田宇太郎が博物館明治村の設立に関与していたことは以前から知っていたのですが,この復刻出版物を実際に入手したことで,日本郷土文藝叢書刊行会の存在を知るとともに,明治村だけで頒布される異版が存在するということに興味を持ちました.
私は以前に『情報メディア研究』に発表した論文のなかで,日本近代文学館による復刻出版事業を取り上げたことがあります.そのときの問題意識が呼び起こされ,近代文学作品の復刻出版の歴史において,日本郷土文藝叢書刊行会の存在がどのような流れに位置づけられるのが気になり始めました.そこで野田宇太郎によるほかの復刻出版物も順次買い集めまして,その存在の確認ができた全9作品(そのうちの2作品については再復刻版を含みますので合計11種類)が手元に集まったことで今回の発表につなげました.
3. ポスター発表の研究の概要について教えてください。
国立国会図書館サーチやCiNii Researchを用いて日本郷土文藝叢書刊行会について調べてみると,検索結果はいずれも0件であったことから,そもそも野田宇太郎が手がけた復刻出版物は,これまでにほぼ話題になっていないことがわかりました.国立国会図書館デジタルコレクションの検索結果では9件ヒットしますが,半世紀以上も前の取り組みであることを考えれば,言及している文献数はだいぶ少ないように思います.
そこでまずは日本郷土文藝叢書刊行会による全9作品の復刻出版物の全貌を一覧にして,同時代の日本近代文学館の復刻出版事業を比較できる形で示しました.最初の復刻出版物は1960年の『一握の砂』函館版なのですが,これは1968年に開始された日本近代文学館による大規模な近代文学作品の復刻事業よりも8年ほど先行していることもわかりました.また,それら日本郷土文藝叢書刊行会による復刻出版物について,全国各地の図書館での所蔵状況を知るために,カーリルローカル,CiNii Books,国立国会図書館サーチを活用した調査結果をまとめました.この所蔵調査により,頒布地を限定した出版物であっても,全国の図書館に所蔵されていることがわかりました.
4. デザイン面などで工夫した点を教えてください。
全9作品の復刻出版物の全貌を視覚的にわかりやすくするために,そのすべての表紙と奥付の画像を,ポスターの右半分の領域のすべてをつかって,可能な限り大きめのサイズ(1作品につき高さ10cm)に並べました.遠くからでもたくさんの本が並んでいることが,これによって視覚的にわかりやすくなったと思います.
それ以外の復刻出版物の年表や全国各地の図書館の所蔵一覧など,詳細な情報はポスターの左半分にまとめて配置したのですが,こちら側はいずれも掲載している情報量がやや多いため,文字の大きさは13ポイントから20ポイントまで抑えなくてはなりませんでした.ポスターとしては文字のサイズがやや小さめになっていると思いますので,目の前まで近づかないと内容が判読できないくらいなのですが,これはこれでメリハリのあるデザインになったと思います.右半分は画像を多用しながら情報を大きめに見せることで視覚的に遠くからでもわかりやすく,左半分は小さめの文字であっても伝えるべき情報をしっかり盛り込むように心がけました.
5. ポスター制作にあたっての苦労話やエピソードなどありましたら、教えてください。
復刻出版物の原本の大きさはすべて異なっているのですが,スキャンした表紙や奥付の画像は,縦または横のサイズを統一したほうが見た目としてきれいな印象になります.取り上げた9作品の画像は,そのすべてが同じ高さに揃えるように調整しました.スキャンした画像をそのまま使用すると,どうしても文字が斜め向きに配置されてしまったりもするので,小数第一位まで角度を微調整して,できるだけまっすぐに見えるよう気をつかっています.
また,表の部分以外は発表タイトルや氏名も含めてすべて縦書きの書式に揃えました.横書きにして視線を左から右に誘導するよりも,縦書きにして上から下に視線を誘導したほうが,ポスターの縦の長さを有効につかえるのではないかと思っています.
6. ポスター発表時の会場の人からの反応はいかがでしたでしょうか?
率直に「これはおもしろい発表ですね」という称賛の声をたくさん聞けたのがよかったです.説明のなかで,日本郷土文藝叢書刊行会というキーワードが国立国会図書館サーチやCiNiiでヒット数が0件だったとお伝えしたのですが,これまでに誰も言及していないという事実はだいぶインパクトがあったようです.近代文学作品の復刻出版物は,私の博士論文のなかでも日本近代文学館の出版事業という切り口から取り上げているもので,十数年にわたって関心を持っているテーマの一つなのですが,今回のポスター発表によって,そのときの研究成果を少しだけでも更新できたように思います.
7. ポスター発表の論文発表のご予定は?
今回のポスター発表のためにまとめた資料ですが,発表当日に会場でいただいたさまざまなご意見も反映させた上で,『情報メディア研究』に投稿しておきたいと考えています.今回はありがとうございました.